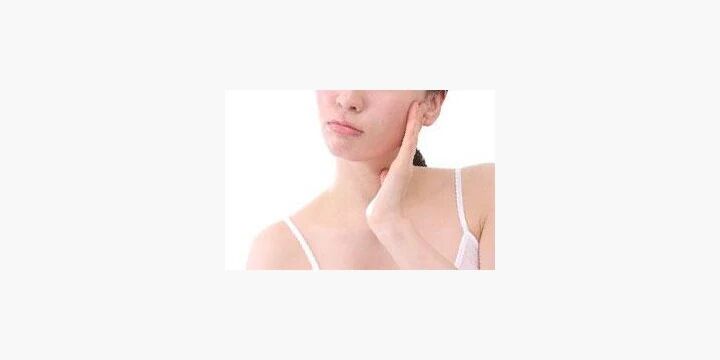慶長年間(1596〜1615年)に創業し、仏教専門書の出版などを手がけてきた老舗出版社「法藏館」(京都市)の公式アカウントが9月24日、こんな投稿をして話題になりました。
「【襲名のご挨拶】 このたび、弊社社長・西村明高が、「6代目西村七兵衛」を襲名することと相成りました。名も「明高」より「七兵衛」へと改めております。」
この投稿を受けて、ユーザーからは「戸籍名も変えるの?」といった疑問の声があがり、同社の公式アカウントは、戸籍名も実際に変更したことを明らかにしています。
老舗企業などで代々の名前を襲名する慣習は珍しくありませんが、改名は誰でも自由にできるものではなく、家庭裁判所の許可が必要になります(戸籍法107条)。
では、なぜ「襲名」が改名の理由として認められるのでしょうか。裁判所の判断を見ていきます。
●改名に必要な「正当な理由」
裁判所の公式サイトによると、「正当な事由」とは、単なる個人的趣味や感情、信仰上の希望等では足りず、改名しないと社会生活に支障を来す場合を指すとされています。
家庭裁判所に提出する「申立書」には、典型例として次のような理由が挙げられています。
・奇妙な名である
・むずかしくて正確に読まれない
・同姓同名者がいて不便である
・異性とまぎらわしい
・外国人とまぎらわしい
・神官・僧侶になった(やめた)
・通称として永年使用した
改名が認められるかどうかは、ケースごとに判断されますが、こうした理由が参考になります。
●「新兵衛さん」の名が地域で定着
昭和27年の大阪高裁決定は、襲名による改名を認めた代表的な例です。
代々「新兵衛」を名乗る家系に生まれた男性は、祖父や父と同じく「新兵衛」と呼ばれていました。地域では郵便局長として「新兵衛さんの郵便局」と呼ばれるほど名前が定着していましたが、戸籍上は別名だったため、日常生活で使っている通称と食い違いが生じていました。
本人は「社会生活に不便がある」として、正式に名前を「新兵衛」に変えたいと裁判所に申し立てました。
一審の家庭裁判所は「商売をしている人なら営業上の必要性から襲名を認める余地はあるが、郵便局長という職業では支障はない」として却下しました。
しかし、大阪高裁は抗告理由書にある「襲名は商売に限られるものではなく、農業や山林経営、地域社会での信用や呼び名など生活全体に関わる」という主張を認めました。
「正当な事由がある」として、戸籍上の名前を「新兵衛」に改めることを認めています(大阪高裁昭和27年2月22日決定)
●「信三郎」襲名に地域と取引先が期待
昭和44年の東京高裁でもこんな判断が下されています。
350年以上の歴史がある味噌・醤油醸造を営む商店では、代々の当主が「信三郎」という名を名乗ってきました。
この家の長男として生まれた男性は、家業を継ぎ、会社組織となった後も代表取締役として経営に携わっていました。地域社会や取引先、銀行、親族も「13代目信三郎」としての襲名を期待していました。
しかし、戸籍上の名前は信三郎ではなかったため、正式に「信三郎」へ改名したいと家庭裁判所に申し立てました。
一審の家庭裁判所は「法人の代表取締役にすぎないので、特に襲名をしなくても営業上の支障はない」として却下しました。これに対して東京高裁は「名の変更は『正当な事由』があればよく、必ずしも特段の必要性や家督相続と結びつける必要はない」と判断。
家業の歴史、地域社会や取引先の期待、親族の同意などを総合すれば、「信三郎」への改名には十分な理由があると認められるとして、原審判を取り消し、名の変更を認める方向で差し戻しました。(東京高裁昭和44年6月11日決定)
●襲名が認められなかった事例も
一方で、襲名が認められなかった事例もあります。
ある男性が仏教の僧侶として得度し、宗派の規程に基づいて僧名に改名したいと家庭裁判所に申し立てました。
しかし、裁判所は、改名が許されるのは「社会生活上、改名しなければ大きな支障がある」と認められる場合に限られると説明。宗教の内部規則があっても、それだけで法的に「正当な理由」とはならないと判断しました。
この男性は新聞販売店を営んでおり、僧籍に入ったものの、実際に僧侶として檀家回りや宗教活動をしているわけではなく、生活の中心は従来どおり商売でした。また改名したいと望んだ僧名を長年通称として使っている実績もありませんでした。
そのため、「改名しないと社会生活に著しい不都合が生じる」とまでは言えず、改名の申立ては却下されました。(東京家裁昭和35年1月19日審判)
●伝統と社会生活をつなぐ「襲名」
老舗の襲名は単なる伝統の継承にとどまらず、地域や顧客との信頼、取引上の円滑さとも深く結びついています。
戸籍名変更が認められるかどうかのカギは「社会生活に支障があるか」。判例が示すように、襲名が実際に生活や仕事の中で機能しているかどうかが、判断の分かれ目となっているのです。